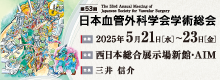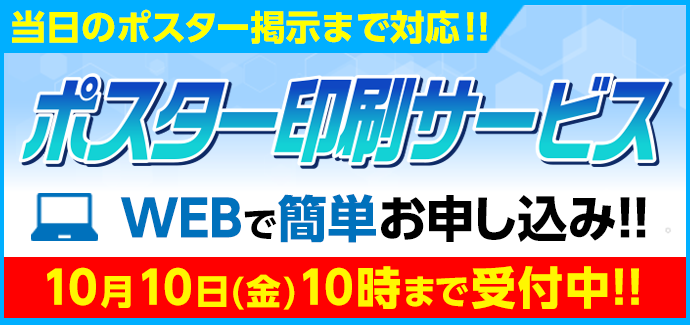指定演題登録期間
2025年4月上旬~
(個別にご案内させていただいた期日までにご登録ください)
演題受領通知
演題をご登録いただきますと、E-mailにて自動的に演題受領通知が送信されます。
演題登録時に必ずE-mailアドレスを確認してください。
登録、修正作業後2日を過ぎても受領通知がない場合は、登録内容に誤りがある場合がございますので、運営事務局(jca66@jtbcom.co.jp)までE-mailにてお問い合わせください。
Gmailをご利用の皆様へ
Gmailメールサーバのセキュリティポリシー強化されており、登録完了メールがスパムメールと判断されメールが届かないケースが多く確認されています。連絡先メールアドレスをGmailとは別のドメインでご登録していただくことをお勧めします。確認メールが届かない場合は、「確認・修正画面」にてログインしていただき登録いただいた内容が最新であるかをご確認ください。
講演形態
学術委員会企画シンポジウム
シンポジウム
| 1 |
医師とAIが融合した脈管領域の診療スタイルの構築
- セッション概要
- 近年、医療分野における人工知能(AI)の進化は目覚ましく、診断や治療の精度向上、医療従事者の負担軽減など、多岐にわたる可能性が示されている。しかしAIの導入が医療現場にもたらす変革を最大限に活かすためには、医師とAIの協働による新たな診療スタイルの構築が不可欠である。本シンポジウムでは、医師とAIがどのように融合し、診療の質と効率を高めるかについて特に脈管疾患の診療に焦点を当てて議論する。
具体的には、AIを活用した画像診断の最前線、ビッグデータ解析による予後予測モデルの開発、そしてAIと医師の連携による個別化医療の実践例などを取り上げる予定である。
|
| 2 |
弓部大動脈瘤に対する治療の最前線
- セッション概要
- 弓部大動脈瘤の治療選択には、外科的手術とステントグラフト術の間で多様な議論が交わされてきた。本セッションでは、外科手術の最新技術と成績、ステントグラフト術におけるdebranch、NAJTUA、自作穴開き、in-situ fenestrationなどの革新的技術を具体的に取り上げ、各治療法の成績と合併症予防に関して議論していただきたい。
|
| 3 |
下肢血行再建術後の抗血栓療法はどうあるべきか
- セッション概要
- 下肢血行再建術後の抗血栓療法において、従来は抗血小板薬がその主体であり、単剤か2剤かとその期間が論じられてきたが、近年小容量のDOACが保険収載されたことにより、複雑になってきている。血管内治療のdeviceも多岐にわたり、従来からdeviceにより異なる抗血小板薬使用法が論じられてきた。本邦においては下肢血行再建術後の抗凝固療法については、バイパス術・血管内治療のいずれについても至適対象となる症例像は確立されているとは言えず、本セッションではどのような症例にどのような抗血栓療法を行うのが最適であるかを論じて頂きたい。
|
| 4 |
ウロキナーゼ供給停止下における急性動脈閉塞・深部静脈血栓症の治療
- セッション概要
- 本邦においてウロキナーゼの供給が停止され、同剤が末梢動脈・静脈において唯一血栓溶解療法に使用可能であったため、実臨床において治療に制限がかかることとなった。このため関連各学会から血栓吸引デバイスの早期薬事承認を求め、2023年9月に保険収載された。本邦においては施設を限定しての使用であった。本シンポジウムでは、これまでの経験をもとに、その成績を明らかにするとともに、使用にあたり注意すべき点を明らかにし本邦における今後の診療に役立てていただきたい。
|
| 5 |
静脈血栓後症候群の診断と治療
- セッション概要
- 静脈血栓後症候群 (PTS) は、深部静脈血栓症 (DVT) 発症後の晩期合併症として重要であり、現在でも相当数の患者がDVT発症後に本症に罹患しており、還流障害に伴うADL低下が問題となっている。本邦におけるPTSの発症率や予後については不明であり、抗凝固療法や圧迫療法による介入の意義についても明らかではない。一方で、血栓除去デバイスや静脈ステントが登場し、治療の選択肢が広がりつつある。本セッションではPTSの診断と治療について、現状の問題点や今後の展望も含めて論じていただきたい。
|
| 6 |
リンパ浮腫の診断・治療の現状とこれから
- セッション概要
- ICG蛍光リンパ管造影の登場や顕微鏡の性能が進歩し、リンパ浮腫の治療にパラダイムシフトが起きた。外科治療の普及は、リンパ管や皮下組織に起きている変化の具体的な観察を可能とし、病態の解明に大きく寄与した。しかし、現時点においてもリンパ浮腫には根治法がなく、外科治療を行う医師の偏在という新たな問題も生まれている。本シンポジウムではリンパ浮腫に悩む多くの患者のために、原点に立ち返ってより多くの医療者が使命感を持って診療に臨むことができる知識を学び、実践していく方法を検討する。
|
| 7 |
CLTI症例に対する血行再建:長期QOL維持を目指す工夫
- セッション概要
- CLTI症例に対する血行再建は、血管内治療・バイパス術いずれにおいても救肢の面では比較的有効な早期成績が示されてきた。血管内治療では再狭窄、バイパス術においてはグラフト狭窄や吻合部狭窄などの病変にかかわる問題のみならず、患者さんのQOLに大きく関与する遠隔期の歩行状態、創(断端)治癒などを維持することが望まれる。これらに対して行われている各施設での工夫を示していただきたい。
|
| 8 |
心臓再生医療のbench to bedside:基礎研究から臨床治験の成果まで
- セッション概要
- 本邦で開発されたiPS細胞は疾患研究、再生医療に大きな発展を見せ、様々な領域で研究が展開している。心血管領域においても、iPS細胞から心筋細胞を作製し、これを用いた基礎研究、臨床応用が積極的に展開され、既に一部では臨床応用が開始されている。本シンポジウムでは、本邦の再生医療研究の第一人者の先生方をお招きし、心臓再生医療に関する基礎研究、大動物を用いた非臨床研究、臨床治験の状況など最新の研究および臨床治験の進展の状況をご解説頂くこととした。これにより、この領域の今後の将来展望を議論したい。
|
| 9 |
脈管疾患における画像診断 update(仮) |
| 10 |
CVT(仮) |
パネルディスカッション
| 1 |
透析血管アクセスの課題
- セッション概要
- 本邦の透析患者総数・新規導入患者数はいずれも2021年をピークに減少に転じているが、それでも35万人弱が透析治療を受けており、年間4万人弱が新規に透析導入されている。一方で透析患者の平均年齢は上昇の一途であり、長期透析患者の割合も高止まりが続いている。そのような状況下において、より長期に使用できるバスキュラーアクセス(VA)が望まれており、VAに対する血管内治療(VAIVT)ではステントグラフトや薬剤コーティングバルーンといったデバイスの適応も拡大されている。本セッションでは、VA造設時の術式選択・VAの日常的評価や保護法・VAIVTにおける工夫など、長期的な視野に立ったVA管理について論じていただきたい。
|
| 2 |
腹部大動脈瘤に対するOpen surgeryとEVARの使い分け
- セッション概要
- 本邦における腹部大動脈瘤の治療は、deviceと技術の進化によりEVARが60%を占めるようになってきた。しかし40%において人工血管置換術が行われていることを考慮すると、各施設において、症例ごとにより良い遠隔成績を求めて術式を決めて使い分けていることがうかがわれる。本セッションでは各施設の選択基準を示していただき、今後の本邦における選択基準を考える一助にしたい。
|
| 3 |
B型大動脈解離に対する至適治療
- セッション概要
- B型解離の治療は降圧、疼痛管理、リハビリの内科的アプローチが基本である。しかし近年ではmalperfusionを伴う場合に限らず、将来拡大が想定されるような解離に対しては早期の外科的介入が推奨されてきている。特にB型解離に対するステントグラフトによる治療は本邦のみならず欧米のガイドラインでも強く推奨されている。本セッションでは解離治療とその予後、特に外科治療介入のタイミング(急性・亜急性・慢性)やその手術方法について議論していただきたい。
|
| 4 |
CLTI no option (desert foot) 症例に対する治療戦略
- セッション概要
- CLTI症例の中で血流再開が救肢に必要である症例の多くは、外科手術・血管内治療の技術的な進歩により血行再建可能になった。しかし足部血管が広範に閉塞に至り、いわゆるdesert footやno option症例と称される症例は大切断を選択せざるを得ない症例も多く、十分な治療戦略が確立されているとはいえない。再生医療、中枢側の血行再建に加えてのNPWTや皮弁、吸着型血液浄化器などの工夫に加えて足部深部静脈動脈化も様々な工夫を凝らして行われるようになってきた。本パネルディスカッションでは、これらの症例に対する治療について論じて、今後の治療につなげたい。
|
ワークショップ
| 1 |
EVAR術後遠隔期成績改善のための工夫
- セッション概要
- 腹部大動脈瘤手術の60%がEVARで行われるようになってきた。Deviceの進歩のみならず、術後の遠隔期成績改善のために行われるようになってきた予防的塞栓術などの取り組みや術後のfollowのプログラムなども各施設が工夫して行い、術後拡大に対する二次治療を至適なタイミングで至適な治療が行われるようになってきた結果であろう。各施設の取り組みについてご発表いただき、本邦における今後のさらなる成績改善につなげたい。
|
| 2 |
維持透析症例に対する下肢血行再建:跛行症例におけるストラテジー
- セッション概要
- 維持透析患者は、下肢虚血があるにもかかわらず跛行症状をほとんど呈さず、無症候から突然難治性虚血性壊死・潰瘍に至る症例が多く認められる。一方跛行症例を認める症例においては、治療介入が困難な著明な石灰化病変が多発していることも多い。このため、徐々に症状が階段状に悪化することの多い非透析患者とは異なる血行再建のストラテジーも考慮されうる。維持透析施設と血行再建施設の両者の意見をすり合わせて、今後の診療の糧になる議論を求めたい。
|
| 3 |
血管看護師への期待-看護師による医行為が患者にもたらすもの
- セッション概要
- チーム医療の推進により看護師が、創傷や体液量の管理などの医行為で語られることも多くなってきた。しかし看護学は、看護理論に基づいた枠組みで人を観察し、疾病が生活に与えてきた影響の経緯や今後も含めて看護診断を行い、看護を提供しており、医行為はそのスキルの一つと位置づけられる。医行為の拡大や、無侵襲診断方法の活用によって、患者にもたらされる利益について、ABI測定、創傷管理、VA管理、看護エコーを提示いただき、患者の療養体験への変化を見直す機会としたい。
|
演題登録
総会ホームページからオンライン登録にて受け付けます。
その際は、記載されている注意事項を充分ご確認ください。
| 文字制限 |
- 演題名:
- 全角60文字以内
- 抄録本文:
- 図表なし700文字
- 総文字数:
- 全角1200文字(著者名・所属・演題名・抄録本文の合計)
|
登録可能な最大著者数
(筆頭著者+共著者) |
20名まで |
| 登録可能な最大所属施設数 |
5施設まで |
| 抄録のキーワード |
英語3語以内で2項目入力してください。 |
| 締め切り直前の登録 |
締め切り直前は、アクセスが集中して演題登録に支障をきたす恐れがあります。
不測の事故を避けるため、日時に余裕を持ってご登録ください。 |
登録画面
UMINオンライン演題登録システムでは、【Firefox】【Google Chrome】【Microsoft Edge】【Safari】以外のブラウザで演題登録はできません。
それ以外のブラウザでは、ご利用にならないよう、お願いいたします。
各ブラウザは、最新バージョンの使用を前提としております。
個人情報の取り扱いについて
演題登録にて収集いたしました「氏名」・「連絡先」・「E-mail アドレス」は、運営事務局からのお問い合わせや発表通知に利用いたします。また、「氏名」・「所属」・「演題名」、「抄録本文」は、本会ホームページ及び抄録集に掲載することを目的として利用いたします。本目的以外に使用することはございません。
登録された一切の情報は、必要なセキュリティを講じ、責任を持って運営事務局にて管理いたします。
演題登録に関するお問合せ先
第66回日本脈管学会学術総会 運営事務局(演題担当)
株式会社JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
E-mail: jca66@jtbcom.co.jp
※運営事務局は在宅勤務を実施しております。原則E-mailでお問い合わせいただきますようお願いいたします。